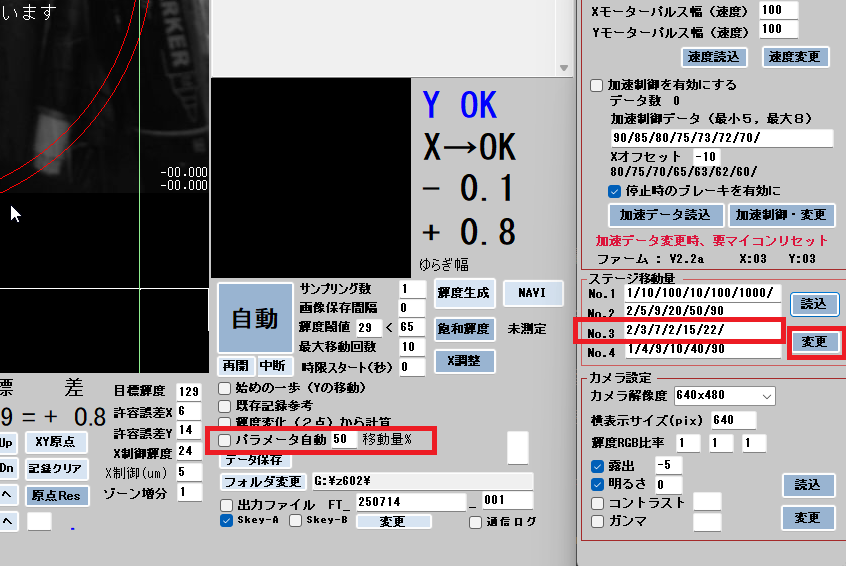
自動測定 (自動パラメータ) 2025.8.3
自動測定では、パラメータの調整が分かりずらく、調整項目が分かっていても、変えてみないと分からず
(変えてみても分からない?)使いにく状態でした。 改善したかどうかも、よくわからない?
今回の方式は、パラメータで計算可能なものは全て、内部で決める方針としました。
調整項目が大幅に減少しましたが、実際の測定によっては、プログラムの調整(変更)が必要になると思います。
これが上手く行けば、使用者は余計な気を使わず、磨きに集中できると思います。
測定の方式は、Yの変化と輝度(R-L)の変化がほぼ直線的になる性質を使い、計算で移動距離を求める方式です。
短時間での測定を狙ったものです。
① パラメータ自動が これを使用する為のチェックです。
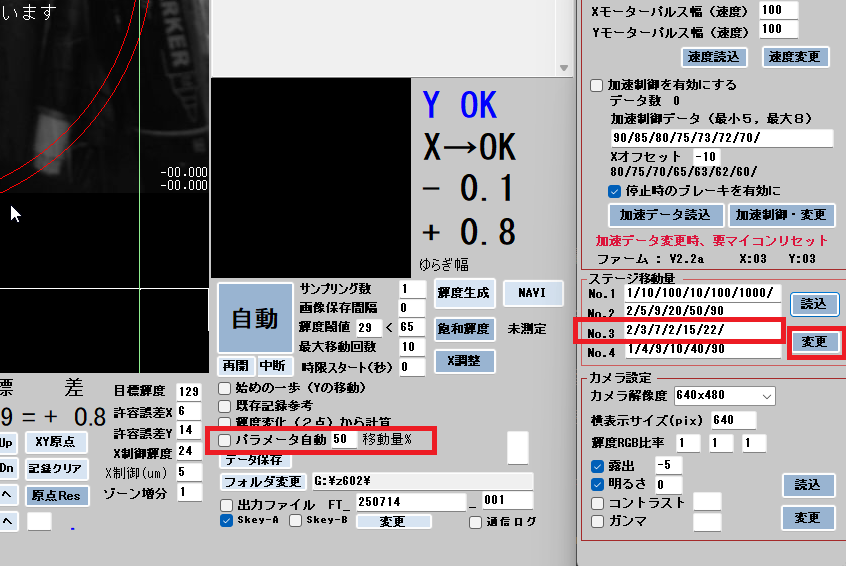
② チェックを入れると この方式で不要なパラメータの表示が消えます。 気にする必要がないんです。
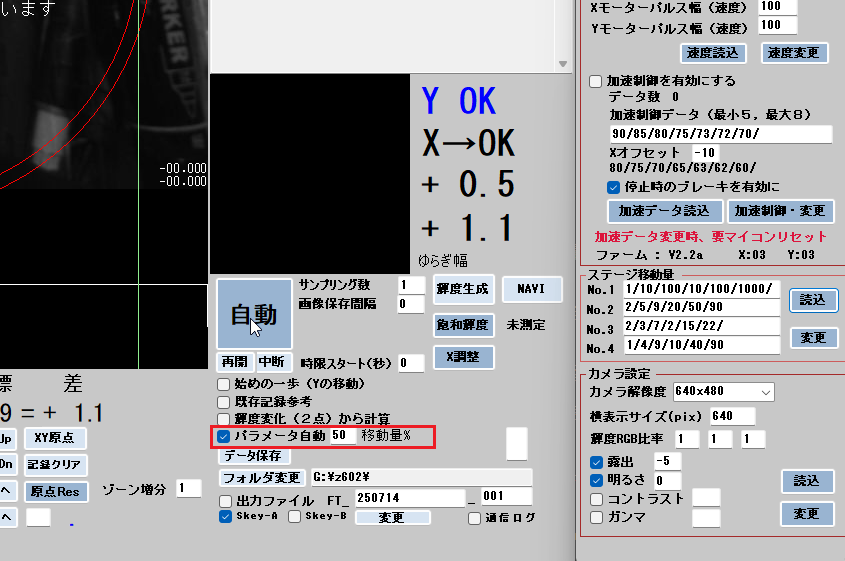
③ 移動量の番号が No.3 に変わります。
テストモードでは移動回数が減ったので、その分を精度向上に当てました。 実際はどうなりますか。
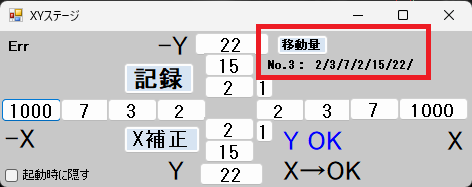
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
使い方
① 準備として ステージ移動量 の No.3 を変えます。 10μm以下にするので No.3 をこれ専用にします。
Yの部分を変えます。数値変更の後に 「変更」をクリックします。
最初Yの移動量を 10/40/90 とかしていたら 2回の移動でOKになりました。 輝度の誤差2程度。
Yの移動量を 2/20/40 にすると 3回か4回の移動で 輝度の誤差1以下になりました。テストモードではありますが。
いきなり2μmにせずに、最初は No.4(10/40/90) と同じでもOKです。
実際の測定ではどうなりますか・・・・・。
2μmで収束すれば、測定精度10um をクリアしたことになるのでは? と思います。
パラメータ自動のチェックを入れます。
移動量の最小の値が、測定の誤差に直接影響します。 これを大きくすれば、測定回数か少なくなり、精度が悪くなります。
状況に応じた値にすることが良いと思います.
② 設定する項目がほとんどありません。
サンプリング数は、残っています。
パラメータ追加しました。 移動量%です。 1回目の移動で全体のどれだけ移動するかの%を指定します。
・100% の場合は、前のゾーンの傾きを使用して、いきなり輝度差0目指して移動します。
これが何処まで、ゼロに近づくが分かりません。
・50% の場合は、 半分移動し そこで正確な傾きを求め、2回目で輝度差0目指して移動します。
・何パーセントが最適なのか 実際に動かして見なければ予想がつきません。 もしかすると 90%辺りが最適
なのかもしれません。1発(1回)で決まるのか? 2回の場合は、どれが一番正確になるか?
② 起動方法
・ これまでと同じで 「自動」 をクリックします。 中断や、再開、測定停止の操作は今までと変わりません。
測定終了後
パラメータ自動のチェックを外す赤枠の項目は変更されています。
又 今までの自動測定の使い方で 「X調整」 をクリックすれば、3項目は、自動で調整されます。
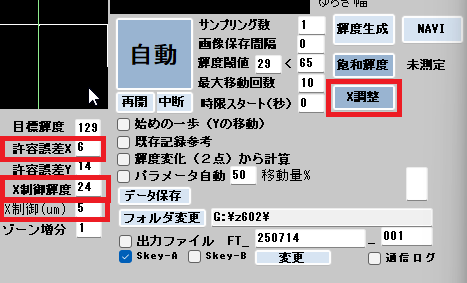
収束しない場合
2つ方法があります
① qcamft.ini 変更
許容誤差Yも内部で計算により決めています。 Yの最短移動の距離が小さい場合は、許容誤差Yが現実に合わない
小さな値になります。 これをそのまま使用すると収束しない場合が有りうると思い、誤差範囲Yの最低値を内部的に設定
しています。
収束しない場合(最小の移動を前後に繰り返す)は、qcamft.ini の1行目の変更(値を大きく) して下さい。
ykidoermin,0,1.6,最低許容誤差Y 旧
ykidoermin,0,2.5,最低許容誤差Y 新
これは 1.6 の値を 2.5に変更した例です。
② 最小の移動量(距離) を小さくする
1/5/11/4/15/30/
1/5/11/2/15/30/
注意点
・開始時の輝度を目標輝度にするので Xをずらしているとその時に輝度が目標輝度になります。
・ゾーンが変った時に、輝度(R-L)が下がりますが、これが飽和した値では、本方式は測定できません。
コントラストを変えるか、測定ソーンの刻みを小さくして飽和しない様にして下さい。
方式
事前測定の表示が最初にでます。 ステージを動かして パラメータの作成をしています。
自動測定では
そのゾーンの1回目の移動で、輝度差のどれだけ移動させるか指定できます。これで輝度とYの変化率が正確に求まります。
2回目はこれを使い、輝度0のなる移動距離を計算で求め、移動します。
これで誤差範囲Yにならなかった場合は、従来の方法でYを動かします。
qcamft.ini にある定数
主にパラメータ自動に関係する定数が、 qcamft.ini の中に存在します。 主に頻繁に変更しなくても良いと思われるデータです。
環境(ステージの精度、光源の明るさ、光源スリット幅、カメラの機種による違い、ステージと光軸のズレ)や、測定者の慣れと
理解により変更が必要な場合もあり得るので、説明しておきます。
変更する場合は、十分注意して変更して下さい。
変更により事態が悪化する場合を考えて、変更前にqcamft.inを別な場所に保存しておくことをお勧めします。
又qcamft-IIを終了させた状態で、修正して下さい。 動作中に修正すると変更が無効になったり、qcamft.ini
全体を失う場合があります。 これは実際に起きています!
[******* パラメータ自動関連 *****],0,,
ykidoermin,0,1.6,最低許容誤差Y
xermin,3,,最低許容誤差X
kidol,-15,, 前進する下限輝度
kidob,-45,, 後退輝度
fstp,0,50,*** autopatam 最初の移動% フォームで変更する***
XlimYk,6,,
X制御最低Y輝度
(注) これは先頭の7行のみです。 全体は100行を超えます。
| 項番 | シンボル | データ名 | デフォルト値 | 意味等 | |
| 1 | ykidoermin | 最低許容誤差Y | 1.6 | 許容誤差Yを計算で求めた後、左の数値より小さい場合は、これに置き換える。 Yが収束しない(最小の移動を繰り返す)場合この値を大きくすれば、改善する場合がある。 |
|
| 2 | xermin | 最低許容誤差X | 2 |
許容誤差Xを実測後計算で求めた後、左の数値より小さい場合は、これに置き換える。 Xの移動が多すぎる場合に、大きくすることにより改善する場合がある。 |
|
| 3 | kidol | 下限輝度 | -15 | そのゾーンの初期状態の輝度(L-R)がこの数値より(絶対値が)大きい場合、は、その位置から Yを前進して測定する。小さい場合は、一旦大きく後退して次の移動で、輝度(L-R)がゼロを狙う。 |
|
| 4 | kido | 後退輝度 | -45 | 項番3で大きく後退する場合に、移動する位置をおよその輝度で指定する。 (絶対値が)小さすぎると、計算精度が悪くなる。 大きすぎると移動が時間がかかり、測定時間が長くなる。 又輝度(L-R)が飽和したり、直線性(輝度と移動距離)が悪くなるまで後退すると、全く測定が 出来なくなる。 項番3より(絶位置)が大きくする必要がある。 |
|
| 5 | XlimYk | X制御最低Y輝度 | 6 | Xの無駄な動きを抑制する為、輝度(R-L) がこれ未満の場合のみX制御を行う。 | |
| 6 |